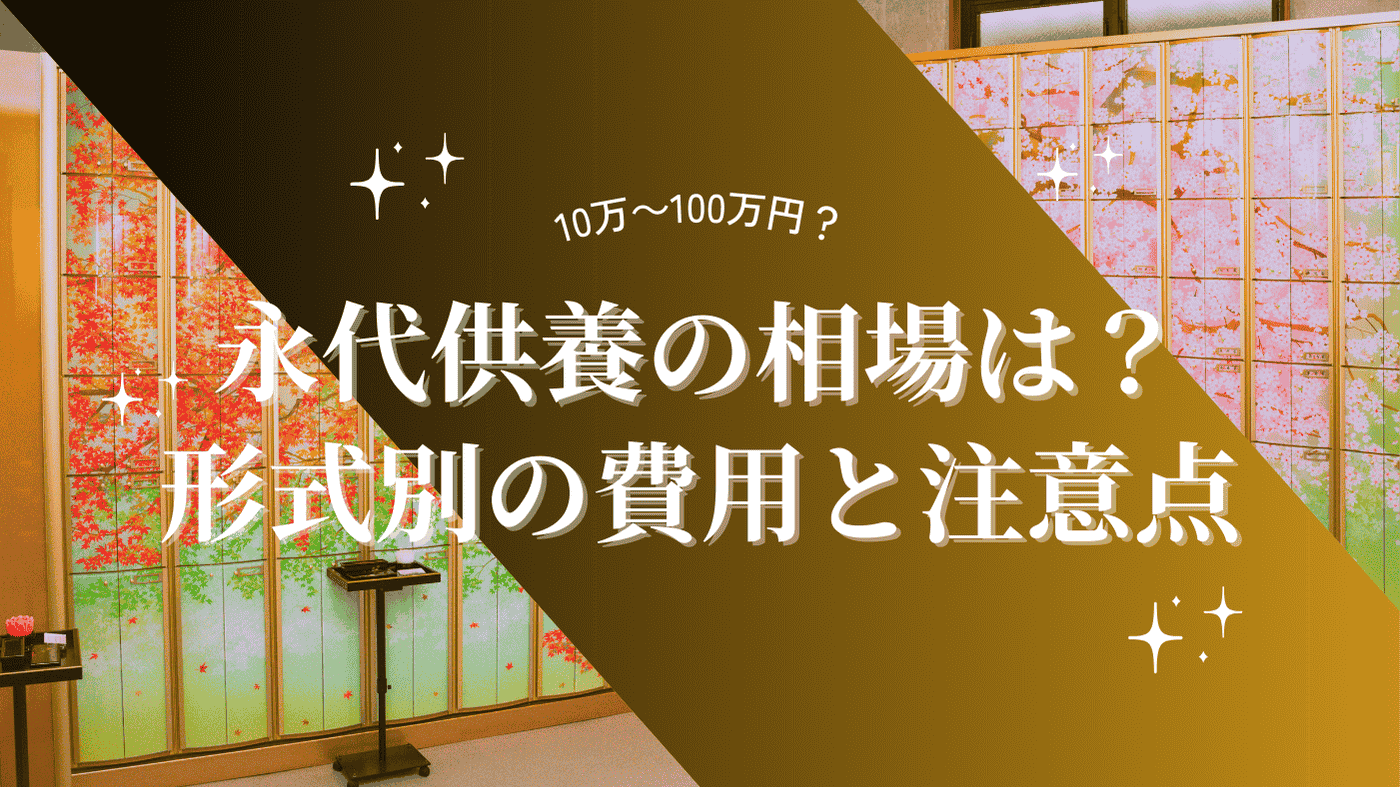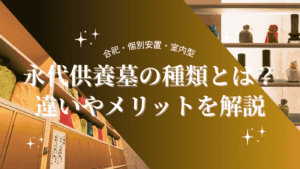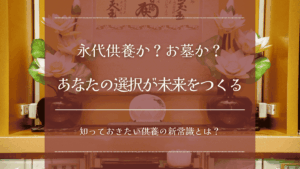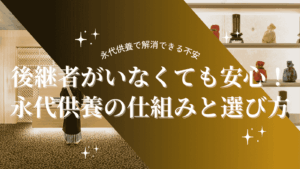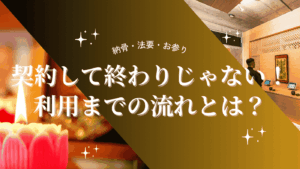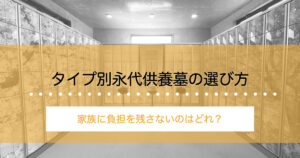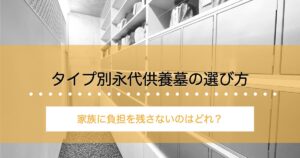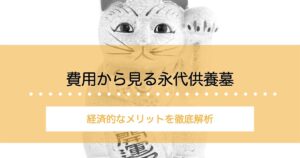渡辺知応
渡辺知応慶国寺の渡辺知応です。
この記事では、永代供養の意味や費用相場、そして検討する際に大切なポイントを分かりやすくお伝えします。
初めて永代供養を考える方にも安心して読んでいただけるようにまとめましたので、ぜひ参考になさってください。
永代供養を考え始めた方へ
永代供養を検討する背景には、本当にさまざまな事情があります。
たとえば、、、
- お墓を継ぐ人がいない
- 子どもに負担をかけたくない
- 遠方に住んでいて管理が難しい
- 自分の代でお墓を閉じるのは気が重い
といった思いです。
現代の家族形態やライフスタイルの変化により、こうした悩みを抱える方は決して少なくありません。
永代供養は、そうした時代の変化に応える形で生まれた新しい供養の方法です。
寺院や納骨堂が責任をもってご遺骨をお守りし、定期的に読経や供養を続けることで、後継者がいなくても安心できる仕組みを整えています。
さらに、合祀型や個別型など形式を選べるようになり、希望に応じた供養の形を選択できる点も、多くの方に支持されている理由です。



永代供養は、単なる“墓じまい”の代替ではありません。
ご家族の負担を減らしつつ、仏さまやご先祖とのご縁を大切にしていく“未来への安心”のかたちです。
慶国寺にも『もっと早く知っていれば心配せずに済んだのに』という声が多く寄せられています。
このように永代供養は、単なる費用面の解決策にとどまらず、「負担を減らしながら心のよりどころを守る」という、現代社会に即した選択肢といえるでしょう。
永代供養とは?
永代供養とは、お寺や霊園が責任を持って故人のご供養とお墓の管理を続ける仕組みのことです。
一般的なお墓は、子どもや孫など後継者が代々守っていきます。
しかし、少子化や核家族化の進む現代では「後継ぎがいない」「子どもに負担をかけたくない」という事情から、永代供養を選ばれる方が増えています。



永代供養という言葉は最近よく耳にしますが、「お寺が代わりに永遠に供養してくれる」という意味合いです。
ご家族に代わって、お寺が責任を持ち続ける仕組みと考えていただくと分かりやすいでしょう。
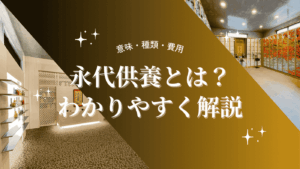
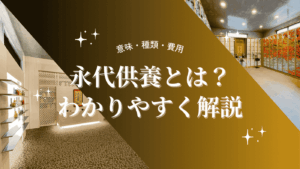
永代供養の費用に含まれる内容
永代供養にかかる費用は、単なる「お墓の購入代金」ではありません。
その中には、寺院や納骨堂が長期にわたってご遺骨を守り、供養を続けていくために必要な要素が含まれています。
つまり「安心を支える仕組みそのもの」に対して支払う費用だといえます。
ただし、何が含まれるかは施設や寺院によって異なり、「すべて込みの一括料金」の場合もあれば、「基本料+追加費用」という形をとる場合もあります。
ここでは、一般的に含まれることが多い内容を整理してみましょう。
永代供養の費用には、次のようなものが含まれることが多いです。
永代供養料(お寺が供養と管理を行う費用)
もっとも中心となる費用です。
寺院が故人の供養を長期にわたって継続的に行うためのものです。
お彼岸やお盆の合同法要、日々のお勤めなど、僧侶による読経や供養の時間・労力が含まれています。
「お寺が責任をもって供養を続ける」という安心を得るための基本料金といえます。
納骨料(遺骨を納めるための費用)
実際に遺骨を納める際に必要となる費用です。
屋外墓地であれば骨壺を収めるカロート(納骨室)の準備や、屋内納骨堂であれば専用の納骨壇の使用にかかる費用が含まれます。
粉骨処理や専用骨壺への移し替えが必要な場合は、その作業料が追加されることもあります。
管理費または護持費(寺院によっては不要な場合もあります)
永代供養の名目で初期費用を納めれば、その後の管理費は不要という寺院もありますが、中には毎年数千円~数万円の護持費を求めるところもあります。
この管理費は施設や建物の維持管理、光熱費や清掃費に充てられます。
契約前に「追加費用が発生するかどうか」を確認することが重要です。
法要料(年回忌など特別な法要は別途の場合あり)
永代供養に含まれるのは「合同での定期供養」が基本です。
個別の年回忌法要や、ご家族だけで営む特別な供養は別途の費用がかかることが一般的です。
法要の内容や規模によって1回あたり数万円が必要になる場合もあります。
「どこまでが含まれているのか」を契約前に確認しておくと安心です。



費用の内訳をきちんと確認せずに契約すると、後から『追加で思った以上にかかった』ということになりかねません。
特に“管理費が別途必要かどうか”と“個別法要の扱い”は、必ず確認しておくことをおすすめします。
費用を考えるときのポイント
永代供養を選ぶとき、どうしても「いくらかかるのか」という金額に目が向きがちです。
もちろん費用は大切な要素ですが、それだけで判断してしまうと、後になって「思っていたのと違った」「家族に負担が残ってしまった」と後悔につながることもあります。
永代供養は、一度契約すると数十年、あるいは半永久的に続いていくものです。
だからこそ「今の安心」だけでなく「将来にわたる安心」まで見据えて検討することが大切です。
ここでは、費用を考える際にぜひ押さえていただきたいポイントを整理しました。



費用の高い・安いにとらわれすぎてしまうと、本当に大切な部分を見落としてしまうことがあります。
永代供養は“これからの安心”を形にするものですから、数字の比較だけでなく、ご家族の想いや状況に合っているかどうかを見極めることが大切です。
永代供養は契約時の金額だけで判断してしまいがちですが、数十年にわたりご遺骨を守る仕組みです。
合祀に切り替わるタイミングや、契約後に追加費用が発生しないかなど「長い目で見た安心感」があるかどうかを基準に考えることが大切です。
将来、誰が供養や管理を担うのかを考えて選ぶことも重要です。
後継者がいない、または子どもに負担をかけたくない場合は、護持費が不要のプランや長期前納制度がある納骨堂を選ぶと安心です。
契約の段階で「家族が困らないか」を確認しておきましょう。
個別安置型の場合、一定期間の後に合祀になるのが一般的です。
その期間が「7回忌」「13回忌」「33回忌」など施設によって異なります。
また、合同供養が毎日行われるのか、年に数回なのかも確認すべきポイントです。
「供養の質と頻度」が金額に見合っているかをしっかり見極めましょう。



費用はもちろん大切ですが、それ以上に“その先にある安心”が重要です。
数字だけで比較するのではなく、供養の内容やご家族の希望に合ったかたちを選ぶことが、後悔しない永代供養の第一歩だと思います。
自分や家族にとって納得できる形かどうかを重視しましょう。
慶松庵の永代供養費用と特徴について
ここまで永代供養の費用相場や内容、ポイントについて全体像をご説明しました。
実際に「自分が選ぶとしたら、どのような区画やプランがあるのか?」と気になる方も多いのではないでしょうか。
慶国寺が運営する永代供養付き納骨堂「慶松庵」では、1霊位からご家族全員まで、さまざまな形で安置できる区画をご用意しています。
また、一般的な永代供養墓とは異なり、慶松庵では 合祀を前提としながらも、できる限り専用骨壷で個別安置を続ける姿勢 を大切にしているのが特徴です。
それでは、実際の区画ごとの費用目安と特徴を順に見ていきましょう。
室内永代供養墓
- 永代供養料:15万円
- 護持費:なし
- 安置霊位数:1霊位のみ
永代供養料は15万円で、護持費は不要です。安置できるのは1霊位のみとなります。
室内永代供養墓は、個人で納める最もシンプルなプランです。
合祀が前提ではありますが、専用骨壷で一定期間は必ず個別安置されるため、故人を大切に尊重した形が守られます。
また、お墓の承継者がいなくても、寺院が永代にわたり供養を続ける安心感が特徴です。
ごえん堂(個別安置)
- 永代供養料:30万円
- 護持費:5千円/年間
- 安置霊位数:1霊位のみ
永代供養料は30万円、護持費は年間5千円で、1霊位のみ安置可能です。
ごえん堂の個別安置は、骨壷を専用袋にお入れしてご安置します。
ごえん堂の参拝室は落ち着いた光と木の温もり中で心いくまでお参りすることができます。
一定期間後に合祀へ移行する仕組みですが、できる限り合祀せずに個別安置を継続する姿勢を基本としているため、安心してご利用いただけます。
特におひとり様の方に選ばれている区画です。
ごえん堂(厨子安置)
- 永代供養料:35万円(1霊位納骨ごとに5万円の諸費用あり)
- 護持費:5千円/年間
- 安置霊位数:骨壷2霊位/専用骨壷8霊位
永代供養料は35万円で、納骨ごとに5万円の諸費用がかかります。
護持費は年間5千円、安置霊位数は骨壷2霊位または専用骨壷で8霊位まで可能です。
厨子安置は、木製の個別厨子にご遺骨を安置します。
参拝室は光と木の温もりがありこの雰囲気の中で手を合わせてご供養するのが大きな魅力です。
複数霊位の安置が可能なため、ご家族単位での利用が多く、故人を身近に感じながらお参りできる空間となっています。
慶松庵(個別壇)
- 永代供養料:50万~65万円(3霊位目から納骨ごとに5万円の諸費用あり)
- 護持費:1万円/年間
- 安置霊位数:骨壷2霊位/専用骨壷15霊位
永代供養料は50万~65万円で、3霊位目以降は納骨ごとに5万円の諸費用がかかります。
護持費は年間1万円で、骨壷2霊位または専用骨壷で15霊位まで安置可能です。
個別壇は、個人やご夫婦で利用するのに適した標準的なサイズです。
合祀を避け、できる限り長期的に個別安置を続けたいと考える方に選ばれる区画であり、ご遺骨を守りながら将来の供養方法を柔軟に考えられる安心感があります。
慶松庵(家族壇)
- 永代供養料:85万円(6霊位目から納骨ごとに5万円の諸費用あり)
- 護持費:1万円/年間
- 安置霊位数:骨壷5霊位/専用骨壷30霊位
永代供養料は85万円で、6霊位目以降は納骨ごとに5万円の諸費用がかかります。
護持費は年間1万円、安置可能な霊位数は骨壷5霊位または専用骨壷で30霊位までです。
家族壇は、家族全員や親族をまとめて納められる大規模な壇であり、「家のお墓」としての役割を果たします。
代々にわたって一緒に安置できるため、家族単位でお参りしたい、あるいは合祀を避けたいと考える方に強く支持されています。
家族全員や親族でまとめて納められる家族専用の納骨壇です。
選べる幅が広いことは、安心にもつながります。
慶松庵ではどのプランも『できるだけ合祀にしない姿勢』を大切にしているので、納得のいく供養方法を選んでいただけます。



各プラン(場所や区画)ごとに費用や安置の仕組みは異なりますが、どのプランにも“安心して任せられる”という共通点があります。
大切なのは、ご家族の想いに合った形を見つけることです。
まとめ|費用は安心を形にするためのもの
永代供養の費用は、おおよそ10万~100万円が相場とされていますが、その幅にはしっかりとした理由があります。
もっとも費用を抑えられる合祀型では、10万円前後から契約できる場合もありますが、一度合祀されると他のお骨と一緒になるため将来的に遺骨を取り出すことはできません。
対して、一定期間は個別で安置できる個別型は30万~70万円程度とやや高くなりますが、ご遺族にとって「自分たちだけでお参りできる安心感」があり、その後に合祀となる仕組みが多く見られます。
さらに、永代使用型は50万~100万円以上と高額ですが、半永久的に個別で供養されるため、伝統的なお墓の形を残したい方に選ばれています。
つまり、金額の差は単なる「高い・安い」という問題ではなく、「どのようにご遺骨をお守りしたいか」「家族にどんな形で供養を残したいか」という意志の違いに表れています。
永代供養は一度契約すると数十年、場合によっては半永久的に続いていくものですから、初期費用だけでなく
「その後の管理費が発生するのか」
「合祀に切り替わるタイミングはいつなのか」
「供養の頻度はどれくらいか」
までをきちんと確認することが、後悔のない選択につながります。
また、費用の中には寺院が長期にわたり責任をもって供養を行う安心料が含まれています。
単に「場所を借りる契約」ではなく、「お寺に供養を託す」という大切な信頼関係の表れでもあるのです。
数字だけにとらわれず、自分やご家族が「心から安心できるかどうか」という視点で選んでいただくことが、最終的に満足のいく永代供養につながるといえるでしょう。



永代供養は、お金をかければよいというものでも、安ければ安心というものでもありません。
大切なのは“費用の先にある安心”です。
どのように供養されるのか、ご家族にとって納得できるかどうかを一番に考えていただきたいと思います。
慶松庵では、安心できる選択をお手伝いできるよう丁寧にご案内しています。